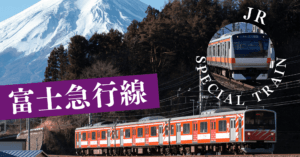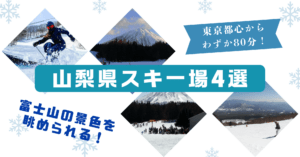神社は、日本の伝統的な信仰である神道に基づいた施設で、目に見えない存在を敬い祈る場所として、古くから日本人の暮らしに深く根付いてきました。神道の根底には、「アニミズム」という考え方があり、木や石、水、動植物など自然のあらゆるものに魂が宿ると信じられています。
このような信仰は、すべての存在に神が宿るという意味を込めて、「八百万の神」とも呼ばれています。自然の神々だけでなく、祖先の霊や偉人の魂までもが神として崇められ、日本独自の多神教的な信仰文化が築かれました。
日本では、就職や受験、安産、厄除けなどの願いごとがあるときや、お正月の初詣などに神社を訪れる習慣が根付いています。こうした風習は、日々の感謝を伝えたり、願いを叶えてもらうために神社に参拝するという、日本人の精神性を表す文化です。
近年では、神社はパワースポットとしても注目されており、御朱印巡りを楽しむ人も増えています。三重県の「伊勢神宮」や、広島県の「厳島神社」などは、観光スポットとしても多くの人に知られています。
また、日本の象徴である富士山が位置する山梨県にも、強力なご利益があるといわれる神社がいくつかあります。その中でも特に人気を集めているのが、「河口浅間神社」です。富士山信仰と深い関わりがあり、豊かな自然と神聖な空気に包まれた、心洗われるようなスポットです。
しかし、実際に神社を訪れても、「参拝方法が分からない」と戸惑ってしまうことはありませんか? 正しい手順を知っておけば、より深く神様に心を通わせることができます。
この記事では、正しい参拝の流れや、神社を訪れた後の楽しみ方について、詳しくご紹介します。
[参拝前の準備]神社にふさわしい服装とは?

神社を参拝する際の服装に明確な決まりはありませんが、神聖な場所を訪れるという意識を持つことが大切です。普段着でも構いませんが、できるだけスーツや清潔感のある服装、自分が持っている中で一番きれいな服装を選ぶと良いでしょう。
穴の空いた服や極端にカジュアルすぎる服装(ジャージ・ビーチサンダルなど)は避けるのがマナー。参拝は神様への敬意を表す行為でもあるため、見た目にも配慮しましょう。
また、多くの神社は自然に囲まれた場所や山の中、川の近くにあることが多く、歩く距離もあるため、動きやすい服装と歩きやすい靴選びも重要です。
さらに、神社を訪れる際には「ハンカチ」と「小銭」を持って行くのが基本。
- ハンカチは、手水舎で手を清めた後に手を拭くため。
- 小銭は、賽銭用として準備しておくとスムーズに参拝ができます。
この2つは、神社参拝の持ち物として必須アイテムといえるでしょう。
なぜこれらが必要なのか、次の項目で詳しく解説します!
[参拝]鳥居・参道

神社に訪れたら、まず目に入るのが「鳥居」です。鳥居は神聖な場所の入口を示しているため、鳥居の前では社殿に向かって一礼をするのが参拝の基本マナーです。
鳥居をくぐると、社殿まで続く「参道」があります。
この参道の中心は、神様が通る神聖な場所とされているため、参道の中央は避けて左右どちらかに寄って歩くことが礼儀とされています。
もしやむを得ず参道の中心を通る場合は、軽く頭を下げて神様に敬意を示すようにしましょう。
[参拝]手水

参拝前には、手水を行います。
- 参拝の前に、手水舎で手と口を清めます。
- 予めハンカチを用意し、手水舎の前で軽く一礼をします
- 右手で柄杓の柄を持ち、水をすくいます。そして、その水でまず左手を洗い、次に左手に持ち替え、右手を洗います。
- 柄を右手に持ち替えて、左手に水を溜めます。そしてその水で口をすすぎます。
- もう一度、左手を洗います。ひしゃくを両手で静かに立てて柄の部分を水で流し、ひしゃくを元の位置に戻します。
- ハンカチで口と手を拭いて、最後に一礼をして終了です。
そして、近頃は新型コロナウイルスの関係などもあり、「流水」での手水も増えました。
以下は流水での手水の方法となります。
- 予め、ハンカチを用意し、手水舎の前で軽く一礼をします
- まずは流水で両手を洗います。次に、両手に水を溜め、その水で口をすすぎます。
- もう一度、両手を洗います。
- ハンカチで口と手を拭いて、最後に一礼をして終了です。
上記の作法は、下記の動画からも確認できます。
[参拝]拝礼

初めに、お賽銭箱があるので、軽く一拝をしてから静かにお賽銭を入れます。
金額は決まっていませんが、「”ご縁”がありますように」という願いを込めて、5円を入れる方が多いです。
次に、鈴がある神社では、鈴を鳴らし、”二拝二拍手一拝”で、拝礼します。
- 神前で深く二度、お辞儀をします
- 両手を胸の高さに手を合わせて、右手を少し手前に弾き、両手を肩幅程度に広げ、拍手を二度打ちます。
- 両手を合わせて祈ります
- 両手を下ろし、礼を一度します
上記の作法も、下記の動画で確認できます。
[参拝後] 御朱印・お守り・おみくじ

神社参拝の後には、参拝の証として御朱印をいただく方も多くいます。御朱印は神聖な記録のため、御朱印帳に記入してもらうのがマナーであり、ノートやメモ帳への記入は避けましょう。
また、神社では運試しとしておみくじを引くことができ、大吉・吉・中吉・小吉・末吉・凶・大凶などの結果があります。
引いたおみくじは持ち帰ってじっくり読み返すのがおすすめですが、境内の専用の場所に結んで祈願する人も多いです。
おみくじには金運や健康運、恋愛運などのアドバイスも記されているため、日々の生活の指針として活用できます。
さらに、神社で授与されるお守りは、家内安全・交通安全・学業成就など目的別に種類が豊富で、人気のお土産としても喜ばれています。
参拝後は御朱印・おみくじ・お守りで神様のご加護を受け、より充実した神社参拝を楽しみましょう。
[おまけ]お寺と神社の違いとは?

日本には神社のほかに「寺院(お寺)」も多く存在します。京都の清水寺や金閣寺は、特に有名な寺院の代表例です。
神社と寺院の大きな違いは、信仰の対象となる宗教が異なることです。
神社は日本古来の「神道」を信仰する場所である一方、寺院は「仏教」の教えに基づいた宗教施設です。
仏教はインドで釈迦によって開かれ、中国を経て日本に伝来しました。寺院は仏教の僧侶が修行や法要を行う場所で、信仰の中心となっています。
山梨県にも多くの寺院があり、特に南巨摩郡身延町にある「身延山久遠寺」は、国宝「絹本著色夏景山水図」などの貴重な文化財を所蔵する歴史的な名刹として知られています。
神社と寺院の違いを理解しながら訪れることで、日本の伝統文化をより深く楽しむことができます。
山梨県のおすすめ神社「武田神社」—戦国最強・武田信玄を祀る人気スポット

山梨県甲府市にある「武田神社」は、戦国時代最強の武将として知られる武田信玄を祭神とした神社です。
国内外から多くの参拝者が訪れる人気の観光スポットで、特に開運や強運アップのパワースポットとして有名です。
武田信玄の強運にあやかりたい方には、社務所で販売されている「強守」が大変人気。勝負運や厄除けを願う多くの人に支持されています。
武田神社は歴史好きだけでなく、パワースポット巡りや御朱印集めにもおすすめの神社です。山梨旅行の際にはぜひ訪れてみてください。
【武田神社】
| 住所 | 〒400-0014 山梨県甲府市古府中町2611 |
|---|---|
| 電話番号 | 055-252-2609 |
| 営業時間 | 8:30〜16:30 |
| 定休日 | – |
| HP | http://www.takedajinja.or.jp/index.html |
まとめ
今回は、神社の参拝方法などを紹介しました。
参拝でリフレッシュしたり、運気をアップした後にも、御朱印・おみくじなど様々な楽しみ方をできるのが神社の醍醐味!
山梨県は、富士山をはじめとした雄大な自然や神聖な神社がたくさんあるため、パワースポット巡りにも最適!パワースポット巡りが好きな方は、富士山巡りと共に、ぜひ山梨県の神社を訪れてみてくださいね。
あわせて読みたい!あなたにおすすめの特集記事